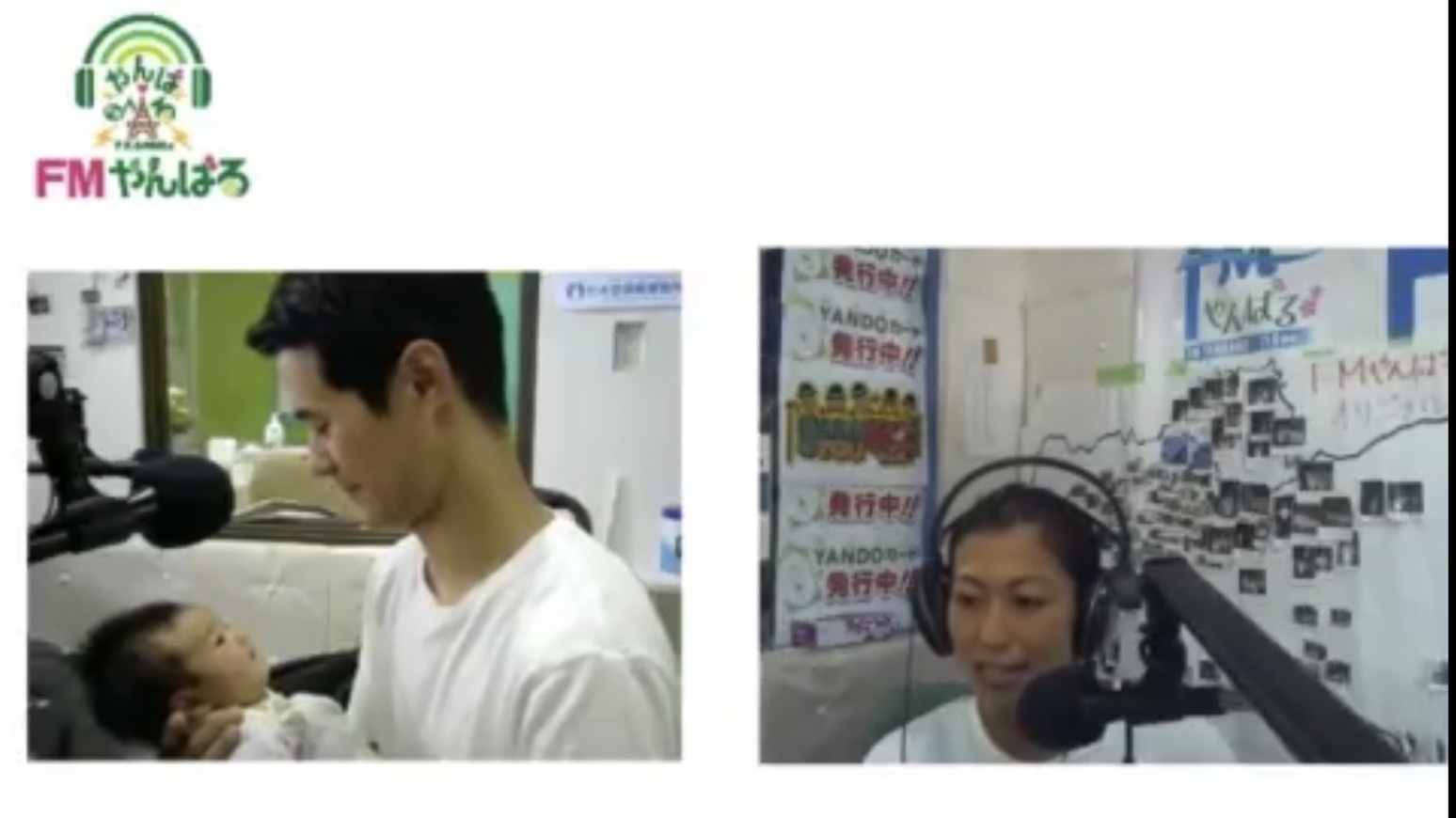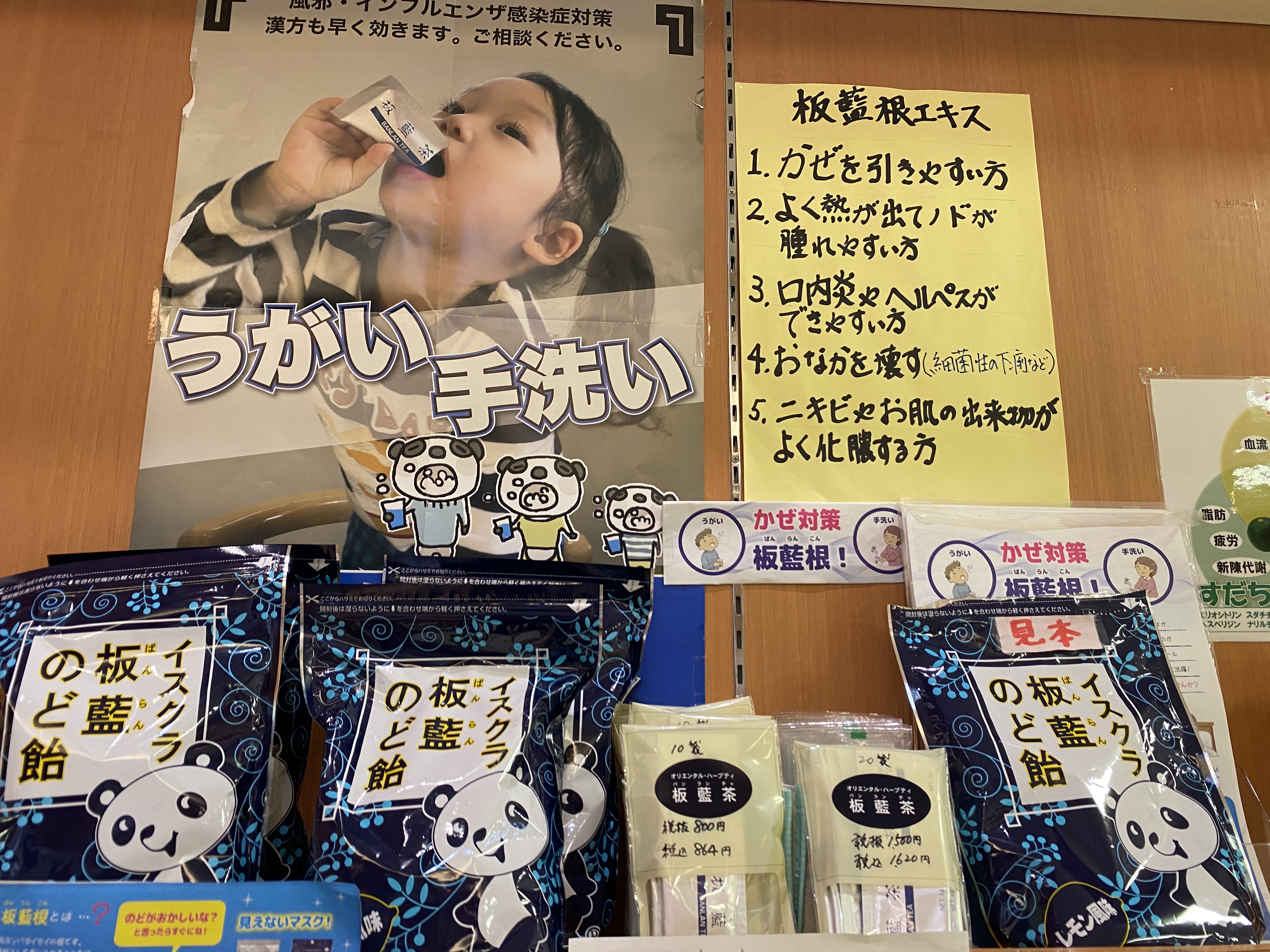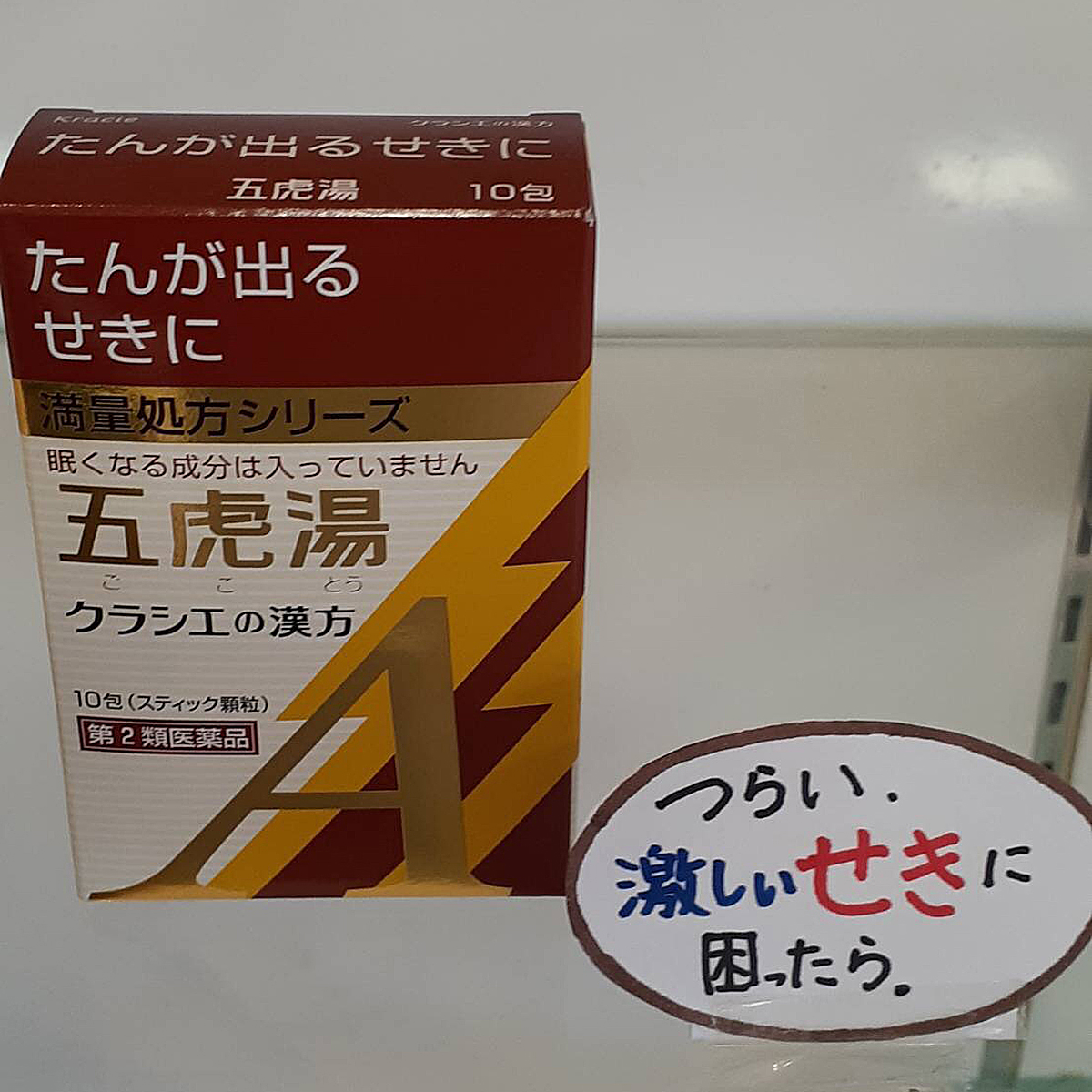「わーっ!」
食卓に並んだキャベツの千切りを見て、南極観測隊の隊員たちから歓声があがります。
信じられるでしょうか?私たちが日常的に食べているキャベツが、地球上で最も過酷な場所のひとつである南極では、これ以上ないほどの「ごちそう」なのです。
🥬南極で起きる「キャベツ絶滅」の日🥬
南極観測隊の調理担当だった渡貫純子さんの著書『南極の食卓』には、胸を打つエピソーdsドが描かれています。
観測隊は1年分の食料を日本から持ち込みます。もちろん、生野菜はごくわずか。
その中でもキャベツは長期保存が可能な、まさに「緑の宝石」です。
隊員たちは「キャベツ・オペレーション」と名付けた作業で、傷んだ外葉を一枚一枚丁寧に取り除き、数ヶ月かけて大切に食べ進めます。
そして、ついに最後のキャベツを食べる日。その日は
「キャベツ絶滅🥬」
と呼ばれ、隊員たちはその貴重な緑を惜しみながら味わうのだそうです。
一面の白と氷に閉ざされた世界では、「新鮮な緑」がどれほど心と体に渇望されるのか。
このエピソードは、私たちに【「緑」の持つ根源的な価値】を強く教えてくれます。
私たちの日常は、本当に「当たり前」か?
この話は、遠い南極だけの話ではありません。
自然災害が頻発する日本に住む私たちにとっても、他人事ではないのです。地震、台風、豪雨…。
いざという時、物流は止まり、スーパーの棚から生鮮食品は真っ先に姿を消します。
避難生活で手に入るのは、炭水化物が中心の保存食ばかり。
そんな時、私たちの体は、そして心は、南極の隊員たちと同じように「濃い緑の栄養」を渇望するはずです。
栄養不足は体力を奪い、判断力を鈍らせます。免疫力が落ち、被災後の環境変化で体調を崩す方が多くいらっしゃるのは御存知の通りです。
緑黄色野菜に含まれるビタミンやミネラル、葉緑素は、ストレスに満ちた非常時において、心身のバランスを保つために不可欠な存在なのです。
しかし、野菜を備蓄するのは現実的ではありません。場所もとり、すぐに傷んでしまいます。では、どうすれば良いのでしょうか?
答えは、20億年の歴史を持つ「命の緑」にありました。
そこで私たちがたどり着いた答えが、「クロレラ」です。
クロレラは、約20億年前から地球に存在する単細胞緑藻。まさに「濃縮された緑黄色野菜」とも呼べるスーパーフードです。
圧倒的な栄養価: ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維、葉緑素など、69種類以上の栄養素をバランス良く含んでいます。
長期保存が可能: 乾燥した粒状のクロレラ。さらに脱酸素処理で酸化を防いでいるため、常温での長期保存が可能です。野菜のように腐る心配がありません。
省スペースで携帯性抜群: 野菜に比べ瓶入り大容量なので携帯性に優れています。保管場所を選びません。避難袋に入れておくのにも最適です。
調理不要の手軽さ: 水さえあれば、いつでもどこでも手軽に栄養補給ができます。
クロレラは、南極の隊員たちが渇望した「緑の栄養」を、いつでも、どこでも、誰にでも届けてくれる、究極の「備蓄できる緑黄色野菜」なのです。
今こそ始めたい。「緑の備蓄」という新習慣。
私たちは、未来に何が起こるか予測できません。だからこそ、備えが必要です。
食料の備蓄を考えるとき、パンやレトルトご飯だけでなく、「命の緑」を備えるという視点を加えてみませんか?
今回ご提案するのは、【クロレラ備蓄ファミリーパック(2000粒×6箱)】です。
1箱2000粒(1,000粒×2本入り): 1000粒1本は大人22.3日分×2本。一箱で45日分(一日45粒食べた場合)。
6箱セット: これで6名家族45日分の「食と緑の安心」が手に入ります。
この6箱が家の片隅にあるだけで、いざという時の食や栄養に関する不安が、どれだけ軽くなることでしょう。それは、ご自身と大切なご家族の命と健康を守るための、賢い投資です。
南極の「キャベツ絶滅」は、遠い国のエピソードでしょうか。 私たちの日常生活が送れて恵まれている時にこそ、有事に備えておきたいところです。
さあ、あなたも「緑の備蓄」を始めませんか?